※バンドルシティのloreアップデート直前ということで9.9時点のバイオグラフィーを記録として残しているものです

特にルルは今のバンドルシティの設定(ヨードルが時空を超越しており数百年程度では寿命を迎えないという所)と矛盾してしまっているのでどう変化するか気になっています
※「ろるゆに」はあくまで個人ブログであり公式と無関係であること、私が多忙な時もあること。突然ストーリーがアップデートされる場合などありますので必ずしもこうやって物語を保存できるとは限らない事をご了承ください。残しておきたいものがあれば各自で保存お願いします。
バンドルシティ
ヨードルの棲み処は一体どこにあるのか、ということについては様々な意見がある。なかには未知の経路を通って、物質世界の彼方にある奇妙な土地へ旅したことがあると主張する定命の者もいる。そこにはやりたい放題の魔法が飛び交っていて、注意を怠れば摩訶不思議な幻影に夢の世界へと引き込まれ、二度と戻ってこれなくなるのだという。
ヨードル以外の生物は、バンドルシティに入るとあらゆる感覚が研ぎ澄まされるとも言われている。色彩はより鮮やかで、食べ物や飲み物は一度口にすればその味を一生忘れることはできず、その後何年も感覚を狂わせる。陽光は永遠の黄金色をたたえ、水はこのうえなく透明で、収穫期にはいつも豊かな恵みにあずかることができる。こうした話は一部だけが真実なのかもしれないし、あるいはすべてが作り話という可能性もある。何しろ人によって見聞きした内容がまるきり異なるのだから。ひとつだけ確かなのは、バンドルシティとその住民たちは時間を超越した存在であるということだ。バンドルシティから戻ってきた定命の者はほとんどおらず、稀に戻ってくることができた者も極端に年老いているのは、それが理由なのだろう。
コーキ
「空より降りたる死!」
~ コーキ
ヨードルのパイロットであるコーキが大好きなものは二つある——飛ぶこと、そして自分の立派な口ひげだ…ただし、この二つの順番は問わない。バンドルシティを離れてピルトーヴァーに移り住んだコーキは、そこで見つけた不思議な機械に夢中になった。彼は飛行装置の開発にすべてを捧げ、スクリーミング・イップスネーク飛行隊と呼ばれるベテランパイロットが集まる航空防衛隊のリーダーになった。銃撃を受けても冷静さを失わないコーキは新たな故郷となった街の空をパトロールしながら、無数のミサイルの雨を降らせれば解決できない問題はないと豪語している。
long
ピルトーヴァーに移り住んだハイマーと仲間のヨードルたちは、科学者としての人生を選び、たちまちテクマトロジー界の発展に貢献する数々の革新的発明を成し遂げた。体の小さなヨードルたちは、それを補って余りある勤勉さを持ち合わせているのだ。“豪気の爆撃手”コーキは、そんな革新的発明の一つである「前線偵察任務ヘリ(通称ROFL)」初号機のテストパイロットを務めたことから、その二つ名を得た。ROFLは後に、バンドルシティ遠征部隊(通称BCEF)の中核を担う航空攻撃機として正式採用されることとなる。現在コーキはスクリーミング・イップスネーク飛行隊に所属し、仲間とともにヴァロランの空を駆け回っている。彼の任務は地形調査だが、そのかたわらアクロバット飛行を披露し、地上の見物人たちの目を楽しませているようだ。
他のスクリーミング・イップスネーク飛行隊員と比べても、コーキは敵から攻撃を受けた際の対応がひたすら冷静であり、ときに異常なほど勇敢である。過去に彼は様々な戦地に赴き、しばしば敵陣への侵入を要する任務に志願しては、情報収集や交戦地帯への伝令を担当していた。危険な状況に身を置くことに生きがいを感じていた彼は、朝の空中戦で一日を始めることを何より好んだという。パイロットとしての腕もさることながら、コーキはヘリにさまざまな改造を施すことも得意とし、愛機には何種類もの武器を搭載していた。これについては、機能よりも見た目のためだと言う者もいたようだ。戦争が行われなくなると、軍人のコーキは退役を余儀なくされた。本人の言葉を借りれば、「エンジンを停止させられ翼をもがれる」ような思いだったという。その後は曲芸飛行や渓谷飛行で空への情熱を満たそうとしたコーキだったが、空気中に漂うかぐわしい火薬の匂いなしでは、どうしても満足することはできなかった。
ルル
「目的地を目指すときに一番いいルートはね… まず逆さまになって、それから隙間を通って、ついでに裏返しになって、もう一周すればいいのですわ!」
~ ルル
ルルは魔法で夢のような幻想や空想の生き物を作り出すことで知られるヨードルのメイジで、ピックスという妖精の相棒と一緒にルーンテラを放浪している。ルルはこの平凡な物質世界を制約だと感じており、気まぐれに世界の法則を捻じ曲げては物体を作り出している。周囲の者は彼女の魔法を異常で危険なものだと感じているが、彼女はみんなには魔法が足りないと感じている。
long
どんなヨードルよりも、ルルのマイペースぶりは群を抜いている。バンドルシティで暮らしていた幼少の頃、彼女は一日中、森をひとりで散歩したり空想にふけったりして過ごしていた。他人と関わるのが嫌いだったわけではない。ただ、せわしないバンドルシティでの日常には、活き活きとした空想の世界へ思いを馳せる事が欠かせなかったのだ。ルルは、普通なら誰も気にとめないような場所に、心躍るような発見をする少女だった。鳥の巣箱に閉じ込められたふりをしていた妖精「ピックス」を見つけたのも、そんな彼女の才能のおかげと言えるだろう。ルルの並外れた想像力に感心したピックスは、彼女を自分たちの暮らす世界へと誘い入れたのである。ルルが案内されたのは、森の中の少し開けた場所にある妖精たちのすみか、「不思議の原」だった。その摩訶不思議な空間では、外の世界では決して変わることのない物の大きさや色といったものが、風向きが変わるようにころころと変化する場所だった。心を奪われたルルはすっかりこの場所が気に入ってしまい、ピックスと共にしばし留まることにしたのである。
不思議の原での暮らしは、ルルにとってあまりに心地よく自然なものであったので、彼女はたちまち時が経つのを忘れてしまった。彼女はピックスと一緒に妖精たちのゲーム(それまでは「ただの真似っこ遊び」として片付けられていた類のものだったのだが…)をして遊び、驚くほど腕を上げた。そんなある日、外の世界のことを突然思い出したルルは、自分がバンドルシティでの生活をすっかり置き去りにしていることに気づき、がく然とする。不思議の原にいると、外の世界のことが、何故かすべて遠い夢の中の出来事のように思えてしまえるのだ。「おうちに帰って、ここで知った素敵なことをみんなに教えてあげなくてはなりませんわ」――そう思ったルルがピックスとともに外の世界へと戻ると、そこはすっかり様変わりしていた。不思議の原では時間の流れ方も違っているらしく、彼女が留守にしていた間に、バンドルシティではすでに何世紀もの時が過ぎていたのだ。ルルは懸命に、外の世界の住人たちと打ち解けようとした。だが彼女の努力は不幸な結果を生んでしまう。子どもたちをかくれんぼに誘い、ゲームを面白くしようと彼らを少しの間だけ花や動物に変身させたルルを、子どもたちの親は快く思わなかった。そしてとうとうバンドルシティのヨードルたちは、ルルに街を出て行くよう命じたのだった。こうして居場所をなくしたルルが次に目指した行き先は、ありとあらゆる魔法が飛び交い、特別な才能を持つ者が受け入れられ、しかも称賛を受けることができる場所だった。
ランブル
「うへぇ、オレのアーマーにお前の顔がくっついちまったじゃねえか!」
~ ランブル
ランブルは若くて気性の荒い発明家だ。この気骨のあるヨードルは、ガラクタの山を使って、たった一人の力で電撃ハープーンと焼夷ロケット弾を搭載した巨大なメカスーツを作り出した。廃品置き場で作り出された彼の発明品を冷笑する者がいても、ランブルは気にしない――いざとなれば、火炎放射器で黙らせてやればいいだけだ。
long
ヨードルの中にあっても、ランブルは常に発育不良のはぐれ者だった。そのため、よく虐められた。生き残るためには他の仲間よりも負けん気が強く、機知に富んだ対応力が必要であった。こうして彼はどんどんと喧嘩っ早くなり、気に入らない相手は誰彼かまわずぶちのめすことで有名になっていった。当然のごとく爪はじきにされたが、ランブルは気にしなかった。物いじりが大好きで、機械に囲まれてさえいれば幸せだったのである。やがて、他のヨードルたちは暇さえあればガラクタ置き場で鉄くずを漁っているランブルの姿を見かけるようになる。
ランブルに素晴らしいメカニックの素質があることを知った教師たちは、ピルトーヴァーにあるヨードル科学進化アカデミーへの進学を勧めた。そこでなら、ハイマーディンガーの高名な弟子たちの一人になるのも夢ではないだろう、と。だが、ランブルはその申し出を突っぱねた。ランブルにとってハイマーディンガーとその取り巻きたちは、ヨードルの優れた技術力をタダ同然で人間に売り飛ばしながら、その陰でヨードルが笑い者にされているのを変えようともしない、「裏切り者」と看做していたからである。
ヨードル科学進化アカデミーを卒業した人間たちの一行が、恩師の生まれ故郷を訪ねて船でバンドルシティにやって来た時、ランブルはその人間たちと面と向かって (少なくとも気持ち的には) 対峙してやりたいという誘惑に駆られた。当初は人間たちをじっくり観察するだけのつもりであったが、相手を挑発するような言葉を数回投げかけてしまった。四時間余りの激しい口論の末、ハイマーのような「立派な」ヨードルたちにとってランブルがいかに恥さらしかを耳に散々叩き込まれた上、ボコボコに殴られ血だらけで帰宅した。
翌朝、ランブルは密かにバンドルシティを発った。それから数ヶ月して街へ戻って来た時、ランブルは、ガシャンガシャンと音を立てながらかっ歩する、巨大なメカのコクピットに座っていた。そして呆気に取られる野次馬をかきわけながら、街の中心部へと行進していき、高らかに宣言したのである――ヨードルの卓越した技術力を世界に知らしめる、と。
ティーモ
「楽しい仲間か、それとも血も涙もない殺し屋か。ティーモは紙一重でその間を揺れているけど、あたしにとっては最高の友達なんだ」
~ トリスターナ
どのような恐ろしい危険や脅威が待っていようとも、ティーモは底知れぬ情熱と陽気さで世界を偵察し続ける。揺らぐことなき道徳観を持ったこのヨードルは、誇りを持ってひたむきに「バンドルの偵察兵の掟」を守っている。時には自らの行動が周囲に与える影響に気づかないこともあるが…。そもそも偵察兵の必要性自体を疑問視する声もある中、ひとつだけはっきりしていることがある——ティーモの強い信念を侮る者は、痛い目を見ることになる。
long
バンドルシティに暮すヨードルの同胞達にとって、ティーモは生ける伝説である。普通のヨードルと比べて、彼はほんのちょっぴり特殊なのだ。ティーモは他のヨードルとの仲間付き合いを好むが、同時にバンドルシティの防衛においては、ヨードルには珍しく単独任務を願い出ることが多い。また普段は極めて温厚だが、戦闘中はスイッチが入ったように冷徹になることでも知られている。警備任務中に何者かの命を奪うことになっても、まるで職務上の事として割り切っているようなのである。新兵だった若かりし頃も、普段は情に厚くて気さくな人柄である一方で、ひとたび戦闘訓練が始まると、表情を一変させて任務に没頭するという性格のギャップがあり、教官や他の訓練兵たちを一様に困惑させたという。しかしその適性を見抜いた上官たちは、すぐさまティーモを「マザーシップ偵察隊」に推薦したのであった。これはバンドルシティにおいて、メグリング強襲部隊と双璧をなす精鋭特殊部隊である。
通常、ヨードルは単独での斥候任務を苦手とするが、ティーモはそうした任務でこそ優れた能力を発揮した。これまでに幾度となく侵入者からバンドルシティを救ってきた彼の功績を見れば、彼は紛れもなく「現役では最も危険なヨードル」の一人なのである——馴染みの宿屋でハチミツ酒を酌み交わす彼の姿からはとても信じられないことだろうが。トレードマークの吹き矢に塗る「アジュンタ」という珍しい毒も、彼がわざわざクムングの密林から直々に採集しているものだ。なお、孤独に過ごす時間が長いティーモだが、最近は同じくバンドルシティの特殊部隊員であるトリスターナとの交友を深めている。ティーモは小柄ながらも多くの者に恐れられる存在であり、その小さな体には想像もつかないような恐るべき意志の強さがある。
トリスターナ
「ブーマーがよろしくって」
~ トリスターナ
他のヨードルたちは自らのエネルギーを発見や発明、またはただのいたずらに注いでいるが、トリスターナはいつだって偉大な戦士の冒険に憧れていた。彼女はルーンテラの様々な派閥や戦争の話を聞き、自分たちヨードルだって、そこで価値のある伝説を残せるはずだと考えた。信頼する愛砲「ブーマー」とともに初めてこの世界に足を踏み入れた彼女は、断固たる勇気と楽観主義を胸に戦闘に飛び込んでいく。
long
小柄ながら大砲を軽々と操るこのヨードルは、偉大な存在というものが姿や形、大きさを問わないものだと教えてくれる。動乱の世にあって、トリスターナはどんな困難にも敢然と立ち向かってきた。彼女は、鍛え抜かれた戦闘能力、揺るがぬ勇気、そして底抜けの楽観主義、この三つの権化といえる。トリスターナと愛砲「ブーマー」にとっては、あらゆる任務が、英雄が実在することを世界に示すチャンスなのだ。
ベイガー
「心の闇を否定するとは…」
~ ベイガー
激情的なヨードルの魔導師ベイガーは、ほとんどの者が近寄ることすら躊躇するほどの力を手にしている。自由の民としてバンドルシティに暮らしていた彼は、かつて定命の者たちが実践する天界魔法を詳しく学びたいと望んでいた。しかしイモータル・バスティオンに幽閉されたことで、天性の好奇心は屈折してしまった。星々の暗き怒りを操る頑固者となったベイガーだが、今でも見くびられることが少なくない。彼自身は自らをまぎれもなく邪悪な存在だと信じているが、その悪行の真の動機がどこにあるのかを不思議に思う者もいる。
long
ルーンテラのほとんどの種族にとって、ヨードルが恐怖の対象になることはないだろう。ヨードルの棲む地として名高いバンドルシティは不可思議で霊的な場所で、物質世界の各地から集められた珍品や思い出の品が溢れていると噂されている。好奇心旺盛なヨードルが故郷を離れ、しばらくのあいだ定命の種族に交じって暮らすことは珍しくなく、たいていは新しい物語や物珍しい体験談を持ち帰ってくるのだ。
だが悲しいことに、なかには道を見失うヨードルもいる。魔導師ベイガーもそんな一人だ。
数百年前、世界を荒廃させたダーキン大戦が終結したとき、ヴァロランに輝いていたのは天の光だけだった。散り散りになっていた生存者は天を仰ぎ、太古の天界魔法を改めて研究するようになった。ベイガーも天界魔法に興味を惹かれていた。すでに自らを神秘学問の大家とみなしていたこのヨードルは、ノクサス領地内の魔導師集団の一員となった。彼らの技を学ぼうというのである。魔導師たちはこの意欲あふれる新参者のことをとりたてて訝しく思うこともなく、彼は彼で天体の運行が織りなす文様を通じて希望を見出す術を魔導師たちに教えていた。
だが世界を再建しようと多くの人々が汗水を流す一方で、世界を征服しようと画策する者もいた。モルデカイザーという名の残忍な覇王は軍勢を従えて各地を荒らしまわり、彼の支配に抗うものを次々に打ち砕き、隷属させた。そんな暴君にとって、たいした戦いの経験もない魔導師集団などほとんどその眼中にもなかった。しかし呪いの鎧に身を包んだモルデカイザーは、そのなかに目ざとくベイガーの姿を認めたのだ。そのヨードルの本質を見抜いたのである。鉄のガントレットをはめた片手でベイガーをひょいと持ち上げた彼は、他の魔導師たちが剣にかけられるのをよそに、その「戦利品」を持ち帰った。
覇王が新たに築いた頑強な砦に囚われたベイガーは、後ろ暗い目的のために魔法を使うことを強いられた。ヨードルが他のどの種族よりも悪知恵が働くと知っていたモルデカイザーは、ベイガーを物理次元に拘束し、バンドルシティに逃げ込むことすらできないようにした。その地獄のような拘束を受けていたのはベイガーだけではなかったが、このように隔離されることはヨードルにとって何よりもむごい仕打ちだった。ベイガーは意志に反して数々の忌まわしい魔法を使うことを強いられた。そうした魔法は主の領土を強化することや、あるいは単に人々に恐怖を植え付けることが目的だった。
想像を絶するような惨めな状況に置かれたベイガーは、卑劣な行いを重ねるモルデカイザーがほとんど不死身といえる存在にまでなるのを、ただただ見ているしかなかった。それが何十年なのか何百年なのか、もはやベイガーにはわからなかった。だがこの年月に呼応するように、ヨードル特有の魔力や風貌が変化していったのは確かだった…
過去の記憶は薄れていった。自分はなぜヴァロランに来たのか?どこから来たのか?今とは違う生活をしていたことがあるのか?そうした疑問が、月蝕の前の最後の光のようにベイガーの脆い精神にのしかかった。
幽鬼の覇王の追従者が謀反を企て、悪夢のような支配は終わりを告げた。だがそのときにはもう、ベイガーに以前の面影は残っていなかった。その目は爛々と光り、声には邪気のある冷笑的な響きがあった。魔法をかけられた檻から脱出したこの哀れな生き物は、その直後に起きた後継者争いには何の関心も示さなかった。彼はこのとき心の奥底で、あらゆる生物が渇望する安心と自由を求めていたはずだった。
にもかかわらず彼は悪に背を向けるどころか、悪を歓迎したのである。邪悪な魔法使いに相応しい防具を身にまとったベイガーは、自分の知るただ一つの手段を使って名声を得ようと決意した。すなわち非道の限りを尽くし、関わる者すべてに自分を恐れさせようとしたのである。星々の憤怒を呼び寄せて敵に叩きつけ、永遠の時の間隙に閉じ込めてやる――そうベイガーは考えていた。
しかし実際はと言えば、ベイガーは自分を囚われの身としたかつての暴君のような成功を収めることはできなかった。
確かにヴァロランの善良なる人々は、実際ある程度は彼を恐れるようになった。その多くは牧草地を黒焦げにされた者や、跡形もなく邸宅を破壊された男爵などだった。だがときにはなぜか、盗賊集団が森の隠れ家から追い出されたり、野性のマークウルフの亡骸が街の広場に散らばっていたりすることもあった。こうした行為は悪意があるとみるべきか、実質的に有益とみるべきかは判断が難しかった。悪行を重ねようとしているのに、ベイガーはどうしてもあと一歩足りないように見えるのだ。
とはいえこの非道のヨードルが世界最凶の悪党になるという目標を捨てたわけではない。魔性の杖を手にした彼は、万人を自分の前にひざまずかせることしか望んでいない。そして自分を見くびった連中を速やかに葬ることに、大いなる喜びを見出しているのである。
ユーミ
「ネコは黄昏と魔法で、イヌは鳴き声と棒でできている!本は…もともとは木だったんだよ」
~ ユーミ
バンドルシティからやってきた魔法ネコのユーミは、かつてはノラという名のヨードル魔女の使い魔だった。ノラが謎の失踪を遂げたことで、ユーミはノラが所有していた意識を持つ本、「境界の書」の守り手となり、そのページのポータルを通って旅をしながら飼い主を探している。ノラの愛情を懐かしむユーミは、旅の連れとなる仲間を見つけては、光の盾と固い決意で彼らを守るのだった。ブックはユーミが脇道にそれないよう注意しているが、ユーミはすぐに昼寝やら魚やらの楽しそうなことに気をとられてしまう。だがそんなユーミも、最後はいつもきちんと仲間を探す旅に戻ってくるのだ。
long
かつてバンドルシティの片隅に、ぼんやりと光る月光蛾が舞い、数えきれないほどの虹魚が川に溢れる森の渓谷があった。渓谷の緑豊かな木々に囲まれて、一軒の山小屋が建っていた。そこではノラという名のヨードルの魔女が、ユーミという名のネコと一緒に暮らしていた。
生まれながらに守りの魔法の力を持つユーミは、陽だまりで跳ねまわったり、ネズミノ樹の下でうたた寝したりして、何年も気ままな暮らしを送っていた。ユーミは冒険への好奇心をくすぐられると、物質世界と霊的領域を行き来するノラの探検旅行に付いていった。ノラはいつも、割れたカップや色付きガラスのかけらや、おかしなステッチの入った布などの妙な物を探し集めていた。彼女はそんな人間界の品々を心からの敬意を払うかのように検分していたが、どういう目的でそんなことをしているのかユーミにはまるで理解できなかった。それでもユーミは魔法の力で飼い主であるノラを守り、無事に家に帰れば彼女に身を寄せて足元を暖めてやるのだった。
二つの世界をつなぐ道はへそ曲がりで、めったにその入り口が開くことはなく、ネコのようにすばしっこい生き物であっても簡単に行き来できるものではなかった。ユーミは他のヨードルたちが、とある石のアーチに東の星が重なるのを待ちわびながら空を眺めたり、ヌマユリの茂る沼地に足を踏み入れて泥に咲く銀の花を探したりする様子を見ていた――とにかく「時」が来なければ、通路は現れないのだ。だがユーミの飼い主であるノラは、「境界の書」を持っていた。それは、ページに描かれた場所ならどこへでも、あっという間に移動できる強力な魔書だ。ノラがポータルとなるその本を開けば、ユーミは嬉々としてノラと一緒に輝くページの中に飛び込み、二人が目的地に到着すると、後から本もついてくるのだった。
ユーミはその本のことを特に気にかけたこともなかった。そう、あの星の無い夜までは。その晩、ユーミが自分のピカピカのランプで月光蛾をおびき寄せるのに飽きて家に帰ると、ノラは行方知れずになっていた。動揺したユーミは飼い主の机の上に本が置いてあるのを見つけると、大慌てでページをめくった。何枚かのページが根元から破られてしまっている。「ブック」――困り果てたユーミは本に向かってそう叫んだ。本の題名は読めなかった。彼女の声に反応して、ブックと呼ばれた本がもぞりと動いた。そのとたん、その書物の中の考えを自分が理解していることに気がついて、ユーミは驚いた。話すことはできないが、ブックは考えをはっきりと伝えることができた。ブックが言うには、ノラはどこか危険な場所を訪れ、移動した後でポータルを壊したのだそうだ。
ご主人さまを助けに行かなくちゃ、そう思ったユーミはブックに助けを求めた。ブックのページは何千枚もあり、その一枚一枚が物質世界と霊的領域にはりめぐらされた魔法の導線によって、さまざまな場所へとつながっている。ノラが移動に使ったページは失われていたが、ブックがいれば近くまで行けるかもしれない。ユーミとブックは可能性のある場所をしらみつぶしに探すことにした。はからずもブックの守り手となったユーミは、ライオンのような勇気でブックを守ってみせると誓いを立てた――もしブックが悪者の手に渡るようなことにでもなれば、バンドルシティへの道が開いて、欲にかられた侵略者たちが誰彼かまわず入ってきてしまうだろう。
こうして彼らは見も知らぬ危険な土地を訪ねてまわる、大変な旅を始めたのだ。ユーミは風の中にノラの匂いを探したが、手がかりは得られなかった。ユーミが息抜きにネズミの匂いを追いかけたり、ちょっとうたた寝をして元気を取り戻したりするたびに、ブックは時間を無駄にしたと言って苛立ち、そのせいで危ない目に会うのではないかと気をもんだ。それでも、ご主人さまを見つけて連れ帰るというユーミとブックの決意は固かった。
ノラの愛情がとりわけ恋しくなってくると、ユーミはよくノラの代わりになる連れを探した。ユーミのお気に入りの連れの一人は、口髭をたっぷりとたくわえ、勢いのよい川のように豪快に笑う、扉を携えた羊飼いだった。ユーミはその肩にちょこんと乗って、氷片まじりの嵐のなか、雪の精霊の怒りから彼を守ってやった。連れのほうは、ユーミのためにピチピチの魚を捕まえてくるのだった。
そうこうするうちに、広大なシュリーマの広大な遺跡で、ユーミはとうとう飼い主の残り香をかぎつけた。ユーミは砂のなかに深くうずもれた青い陶器の破片を掘りあてた。それはノラが持っていたティーポットのかけらのように見えた。だがもっと深く掘ろうとしたそのとき、砂の中から恐ろしい獣が現れ、ユーミとブックは命からがら逃げ出したのだった。あんな生き物がブックのページに爪をたてて引き裂いてしまったら、どんな恐ろしいことになるかもわからない。
ノラへの思いによって結ばれた不思議な仲間のユーミとブックは、今では互いに一番の親友になっていた。ユーミは今日も、飼い主の手がかりを探してあちこちに旅をしている。いつかまた陽だまりの中でノラに寄り添い、うたた寝する日が来ることを願いながら。


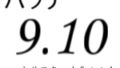
コメント